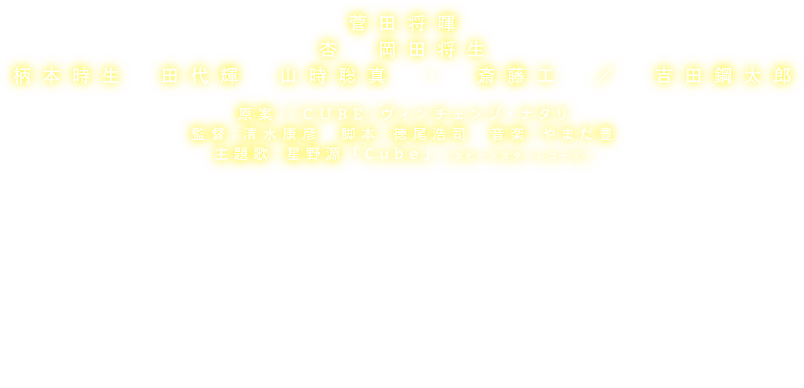最初に「CUBE」の日本版リメイクの話を聞いたときは、どう感じましたか?
まず最初に、本当に嬉しいことだと思ったよ。アメリカでも「CUBE」のリメイク版の話が進んでいたんだけど、そっちはそれほど興味が持てなかった。僕の感覚だと、オリジナルと同じものになりそうな感じがしたから。日本版の場合は、異なる文化的側面を持ち込んでスペシャルで新鮮なものになると思ったんだ。昔、僕が「CUBE」を製作していたとき、ずっと思ってたんだ。日本は「CUBE」を作るのに相応しい場所だって。日本は文化的に「CUBE」の良さをわかってくれると感じていたから。日本と「CUBE」は良い組み合わせになると思ってたんだ。
今回「CUBE」の日本版リメイクではクリエイティブ・アドバイザーとして参加していますが、どのようなアドバイスを送ったのでしょうか?
クリエイティブ面で僕が参加したのは大きな外枠についてのみ。脚本にコメントをしたり、トラップについての提案をしたり。オリジナル版で使用しなかったトラップのデザインをすべて提供した。もし使えそうだったら使ってください、って言って。ただ、クリエイティブ面に対する僕の意見を押しつけたくなかった。誰かがすでにやったことを、再びやって欲しくなかったから。新しいことをやってくれるのを見たかった。監督の清水さんは、これをやり遂げてくれたんだ。あまりネタバレはしたくないんだけど、清水さんの最初の監督作も好きだし、日本版も「CUBE」のキャストは素晴らしい。すべてが一つによくまとまっている。僕はただのチアリーダーだよ(笑)。
日本版リメイクを気に入ったんですね!
好きだよ!オリジナル版で上手く機能したものがなにかとてもよく理解してくれていたと思う。ストーリーの根本的な部分もうまく機能していたし、デザイン的な部分もそう。リメイクとしてうまくいったと感じたが、こうなることは想像していた。異なる文化の中での置き換えが、うまくはまりそうだな、と。キャラクターもそうだし、キューブの中での彼らの衝突もある。オリジナルとは異なる種類の映画だ。そういう意味で新鮮だった。清水さんはクレバーだと思ったね。脚本もとてもフォーマルでよくコントロールされていて的確。このストーリーを語る上ですべて必要なものだ。彼は素晴らしい仕事をしたよ。
オリジナル版と日本版リメイクには多くの異なる点があります。キャラクターも彼らの背景も物語の展開も。これらの違いについてはどう思いましたか?
あまりネタバレになりそうなことは言いたくないんだけど、新しかったのは世代間の衝突だね。これが物語の一つの軸になっている。古い世代がいかに新しい世代を虐待しているか。両世代の鬱積が衝突を引き起こしている。これは21世紀の日本を具体的に現しているのは間違いない。多くを占める高齢者が少数派の若い世代に支えられている。そのような人口動態が、非対称な(asymmetrical)機能障害を引き起こしているんだ。これは僕の作品にはなかったアイディアだよ。僕がも「CUBE」を作ったとき、世代間の衝突という考えはまったくなかった。清水さんの映画は、この点にフォーカスして強い社会的な意思表明をしている。とても良い意味でね。
気に入ったシーンや瞬間はありましたか?
ストーリーの転換は興味深かった。とても良かったね。あと、エモーショナルなストーリーだ。心温まる瞬間がある。清水さんは、も「CUBE」は他の要素と同じかそれ以上に人間ドラマが重要だと理解していたんだと思う。キューブの中にいるキャラクターたちがお互いの関係を発展させていく様を描くのが上手だと思ったね。これが映画の“エモーショナル・パンチ”になっている。例えば、以前作られた「CUBE」の続編では、「CUBE」で機能していた要素を誤解していた。複雑な性格描写を無視し、あまりにも幻想的にしてしまった「CUBE」のキーは、他のSF映画と同様に、なにができるのかというアイディアを弾ませ、これを維持すること。トラップは内臓を揺さぶるような高いショック度と信憑性がないといけない。僕は関わってないけど、「CUBE」の二作目はマジカルすぎて、なんというか抽象的だった。一作目にあったパワーを失っていた。自分が観客の立場になればなるほど、映画そのものよりもキャラクターと一緒にその場所に自分がいるとより感じることができる。日本版の「CUBE」はこの点が上手くいっていると思うね。
日本版「CUBE」のキューブのデザインはどうでしたか?
良かったよ! オリジナルで上手く機能していたところを理解していて。オリジナル版のデザインが非常に知的なのは、プロダクション・デザイナーのヤスナ・ステファノヴィクが混沌としたデザインにしてくれたこと。キャラクターが箱の中の格子につかまって立っているだけじゃ、視覚的に退屈だ。そこで彼女は壁のパターンに非対称性と混沌さを加えてくれたんだ。ちょっとした良いスパイスになっている。トラップのカモフラージュになっているわけだから、理に叶ってるよね。これは「カリガリ博士」(*1919年のドイツの革新的なサイレント映画)の手法を使ったんだ。診断とか非対称なフォームとか。日本版「CUBE」のデザインはオリジナルを踏襲しつつ、フラクタルをデザインに落とし込んでいたが良かったよ。この新しい「CUBE」は少し相互作用的で、キャラクターの感情に反応している、という描き方もスマートで興味深い。この相互作用(インタラクティブ)である、という点は、まさにキューブが人間の行動研究に関するある種の実験である、ということの証明でもある。実験というか厳密に言うと“事例”だね。この部分も僕たちの「CUBE」では語られなかった要素だ。ほかにも、キューブがキャラクターの感情に反応している表現として、撮影監督の栗田豊通さんが緻密に照明をデザインしている。
あと、彼らがやった正しいことを挙げさせてもらうと、それぞれの部屋で壁の色を変えているよね。そうしないと観客がすごく混乱するし退屈するからだ。「CUBE」という映画の監督とプロダクション・デザイナー、撮影監督にとって一番チャレンジングなのは、いかに映画を大きく見せるかではなく、いかに面白さを維持するかだ。だから空間の見せ方を変え、照明の色を変え、驚くほど視覚的に変化を作らなければいけない。「CUBE」の最初の続編は、僕は関わってないんだけど、ハイパーキューブの色をすべて白くしていた。そのため、どの部屋もとても匿名的になってしまった。一方、日本版の「CUBE」はそれぞれの部屋に個性があり、照明の色を通してビジュアル的なアーク(物語の横糸)をストーリーに加えているんだ。
「CUBE」は監督にとって長編デビュー作です。パッションとエネルギーを存分に注ぎ込んだ重要な作品だと思いますが、この映画はどのように生まれたのですか?
こういう言い方をするのも嫌だけど、低予算の映画を作るためのアイディアを考えているときに浮かんだんだ。一つのセットで作れる映画のね。でも、舞台劇のような映画は作りたくなかった。人が座って喋ってるだけのような映画は御免だった。動きがあって、映画的にちゃんと繋がれるような作品を作りたかった。そこで一つの部屋を再利用したらどうだろう、一つのセットで多くの部屋を表現するのはどうだろう、と考えて、同一の部屋で構成された迷路というアイディアを思いついた。部屋が同一ということは対称性があるという意味で、それで必然的に形状としてはキューブがふさわしいと感じた。小さなキューブがより大きなキューブを作り上げている。このアイディアは本当にすぐに思いついた。それから数年後に、友人のアンドレ(・ビジェリク)が三幕ものストーリーを考えてくれた。最初のストーリーは幻想的なテリー・ギリアム風の方向性だったんだけど、アンドレが「物語のパワーはシンプルさだ」と力説してくれて、そこにフォーカスすることにし、できる限りシンプルにすることを心がけた。日本で「CUBE」が評価されている理由は、僕が日本のデザインの良さを理解しているからだと思う。日本ではシンプルであることにリスペクトがあるし、すべてが正確で無駄がない。とにかくその方向でアプローチすることが決まったんだけど、こうなると「CUBE」の脚本は僕が大好きなものから成立していることがわかるよね(笑)。
日本文化との繋がりがここに!
あと、このアイディアが生まれた理由として、僕は映画のストーリーボードを描いていたというバックグラウンドも関係している。この一作目はとてもコントロールされた環境で作らなければいけなかった。そうすることで、すべてのショットを完璧にデザインできるからね。でも皮肉なことに、製作が始まってみると、地獄の撮影現場だった(笑)。まったくコントロールできない環境で、様々な理由から困難な時間を過ごした。セットはとても複雑だった。すべてを正しく作らなければいけなかったのに、ドアがうまく機能しなかったりして。撮影する時間になっても、すべてのことを一瞬で放棄しなければいけなくなった(笑)。ドアを開閉する手段がないんだから。スケジュールも、撮影を優勢に進めるため時間を費やしてきたすべてのバランスも崩壊してしまった。殺されてしまったんだ。砲火の洗礼(厳しい試練。baptism of fire)だった。監督一作目は精神的にも肉体的にもチャレンジングだった。箱の中で撮影するのは簡単だと思うかもしれないけど、実はすごく難しいということがすぐわかる。その環境における照明の性質もだけど、そこに撮影クルーを入れなきゃいけないのもそうだし。びっくりするほど難しかった。低予算の映画にとってはね。今考えても野心的な映画だとは思う。スペシャル・エフェクトもビジュアル・エフェクトも、あの当時の試みとしてはスペシャルで、大胆で困難だった。「CUBE」を製作するのは本当にハードだった。幸せな体験ではなかった。でも最終的には素晴らしい出来事になったけどね。この作品がなければ今の僕のキャリアはないわけだから。
「CUBE」の撮影がいかに大変だったか、ということを少し語ってくれましたが、撮影中最大のチャレンジはなんでしたか?
いつもそうだけど、時間だね。撮影期間は20日しかなかったから。いや、実際には21日かな。30時間ぶっ続けで撮影していた日もあったからね(爆笑)。あれ以来、あんなに長時間連続して撮影したことはないよ(笑)。滅多にない出来事だけど、撮影クルーの一人と個人的に衝突があった(笑)。あと、小さな圧力鍋みたいだったね。セットの中では数百の電球を点けてたから、まるでオーブンの中にいるみたいだった(笑)。プレキシグラスが文字通り溶けたからね(笑)。暑すぎて。とにかく、「CUBE」みたいな映画を作るときは、空間も時間も限定されているから、普段ドラマやコメディの撮影に携わっている人は理解できていなかったと思う。バカみたいと感じていたんじゃないかな。もちろん、みんながみんなじゃないよ。みんなとても献身的だったし。でも、ちょっと、既存の枠にとらわれていなかったかな。評価はされていなかったと思う。SFとホラーというワードを聞くだけで、バカだと思われていたから。価値を理解されていなかった。あの頃、90年代半ばであっても、ホラーとSFは真剣に受け止められていなかった。敬意を払うジャンルだと思われていなかった。今でも過小評価されているところがある。いや、今は昔よりもそうだよね。ハリウッドはこういう映画を作らなくなったから。あの頃は、みんな「パルプ・フィクション」の二番煎じみたいな映画や、サンダンス映画祭用の映画を探していた。ドラマ映画が重要だった。だからホラー映画を作っていると、芸術的にレベルの低いやつだと思われていたんだ(笑)。でも、それはアドバンテージでもあったけどね。自由なスペースがあるわけだから、それは最高だった。開拓時代のアメリカみたいにね。ともかく、そこもハードな部分だった。映画がちゃんと評価されなかったからね。